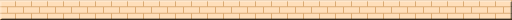
明るさ神話の周辺
乾 正雄
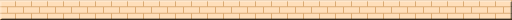
明るいことを単純によいことだと思っている人は、世間一般にも照明界にも多い。私はそれを少し変だと考える一人である。私が天の邪鬼なのだろうか。
もう30年以上前になるが、1972年4 月号の今日の課題で、私は「明るいことはよいことか」と問いかけた。日本で、省エネがいわれだしたのは1973年末のオイルショック以後だし、省資源という言葉の流布はさらに後のことだ。あんな昔に、なぜ私はこわいもの知らずな原稿を書いたのだろうと思うことがある。多分はじめての海外行きでイギリスに住み、若い頭が彼の地の町の暗さの感化を強く受けた結果だったのだろう。
最近になって、私は『夜は暗くてはいけないか』と題する本を出したが、これも同じ路線を踏襲する。明治維新にアメリカやヨーロッパを訪ねたわれわれの先人たちは、どこへ行ってもガス灯が明るく灯っているのに仰天して帰国した。明るさこそ先進文化の象徴だと思いこんだふしがある。その後日本が、街路といわず、ビルといわず、明るさ一点張りの繁栄の時代
−それはおおむね昭和時代に一致する。そのなかの最盛期が大戦後の高度経済成長期であろう−
を謳歌したことは周知の事実だ。それは明るさ神話とでも呼ぶべき風潮だったが、私はその風潮を変だといったのだった。
じつは明治維新ごろのイギリスは大して明るくはなかった。電球発明後のイギリスも、低い山が徐々に適度な高みに達する程度に明るくなったに過ぎない。激変したのは日本の方で、明治維新には街灯ゼロの闇夜の国が、昭和の後半には世界屈指の広告塔の輝く国に変貌した。だから、われわれの先人たちがイギリスの明るさにびっくりしたのに対し、私はといえば「イギリスは暗い」と思ったのだ。
明るさ好きは、例えてみればスピード好きに一脈通じるところがある。飛行機は速くて便利だから、地方にも空港はあった方がよい。新幹線も遠方までのびた方がよい。高速道路も地方の末端までつながるのがよい。与党の政治家や大企業のトップには今でもそう考えている人が大半のようだ。いや、国の産業や経済を支えているような職種の人たちは全員それに「右へならえ」しているといってよいくらいだろう。しかしながら、文科系の学者や芸術家や文士などのなかには、そんなにいそいでどうするんだという、鈍行列車好き、路線バス好き、自転車好きが少なくない。そういう好みは暗さ好きに通じる。物事には両面がある、といっしまえばお終いだけれども、ここはだいじなところだと思う。
『夜は暗くてはいけないか』を出版したとき、照明学会の人たちに共感してもらった記憶は私にはほとんどない。ゼロではないが、とっても少なかった。他方、暗いのはいいじゃないかといってくれた人は意外なところにいた。私の耳に入ったのは主に文筆家の方々の言だが、「なぜぼくは自動販売機の必要以上の光の強さに苛立つのだろうか」と書く椎名誠氏、「家を暗くしようと5
燭の電球を買いに行ったら売ってなかった」と憤慨する中野孝次氏、「夜の明かりに吸い寄せられる連中なんか虫も同然」と言い放つ斎藤美奈子氏、そして、「みんな、闇というものを思い出してみよう」と話を結ぶ池澤夏樹氏、などなど。この国では、世の中の
(比喩的な意味での) 暗さを活字で描くような職種の少数派にして、はじめて照明の暗さも共感をもって言語化されるらしい。
日本国株式会社の主流に属する人々は明るさ好き、主流からはずれた変わり者
(高名な方たちをここに入れて失礼ながら) は暗さ好き、照明への思いには、こんな二極化がある。まだ高度成長期がつづいていたころなら、多数派の明るさ好きは、少数派を変わり者呼ばわりしてすましていられただろう。しかし、時代は移り変わって、速い乗物はもう今程度で十分という人がどんどん増えている。いいかえれば、空港や新幹線や道路などの建設至上主義の時代は過ぎ去った。同様に明るさ神話の時代もいつのまにか過去のものになったといわないわけにはゆくまい。
ただ、遅い乗物にも電気自動車のような未来があるのと同様に、暗い照明にも夢があることをつけ加えておきたい。以下はほんの一例だが。昼間の戸外ほどに明るい光天井をつくることは、技術的に容易でおもしろくもなんともない。ところが、ひとたび天井照明を全廃し 壁掛け照明や、フロアスタンドや、電子ディスプレイなどを組み合わせて暗い環境を構成しようとすると、照明技術はとたんにむずかしくなる。暗くて且つ快適な環境づくりは、照明デザイナーにとってやり甲斐のある、そして多分儲けの大きい仕事なのだ。
